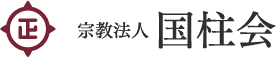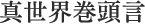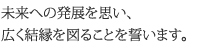2025年09月03日(水曜日)
今年もはや8月を迎えましたが、この月の半ばには御先祖様をお迎えするお盆の行事が全国各地で行われることと思います。ここ東京では新盆が慣わしとなっておりますことから、国柱会本部では7月15日に盂蘭盆開顕大供養会を執り行いましたが、8月15日にも盂蘭盆開顕大供養会(旧盆)が執り行われます。お盆は、亡き人への報恩感謝とともに、私たちが法華経の信仰を新たにする機縁となります大変大切な行事の一つであります。
お盆の起源は目連尊者が母を餓鬼道から救うためにお釈迦さまの教えに従って供養を行ったという『盂蘭盆経』で説かれています説話に基づいていると聞いています。この経が説く趣意は、親を偲んで「孝養」を尽くし、亡き人への「供養」を奨めるところにありますが、本化妙宗を信仰する私達にとって大切なのは、それが単なる儀式で終わることなく、「立正安国」の実践の一環として捉え、活動することだと考えます。
「供養」というと、個々人が自分の先祖の為に徳を積むことと理解されるのが常の様ですが、国や社会の有り方を良くしようとする行動へと広げていくのが本当の供養の有り方だと思います。つまり、亡き人への祈りは、現世に立ち向かう私たちの生き方、そして社会全体の有り方を正していくことの誓いの表明ではないかと理解しています。
近年私たちの社会は便利になり、スピードと効率が重んじられます。その中で、自分中心になりがちで、人と人とのつながりが希薄になって孤独や不安が広がっている様に思われ、「いのちのつながり」や「感謝のこころ」が置き去りなっている様な気がしてなりません。そんな時代だからこそ、今一度「供養」の有り方を見直すべきであり、そのよい機会がお盆でありお彼岸であると思います。供養とは亡き人を偲ぶ行為であると同時に、今を生きる我々の心を磨く行事でもあります。磨かれた心で家庭を照らし、社会に温もりをもたらしましょう。供養の心で家族に接し、友人や隣人など社会で接する人々に思いやりを施し、自分自身に誠実に向き合う行為が大切だと思います。法華経の教えを学び、南無妙法蓮華経とお唱えすることによって、私たちは活かされ導いてもらえるものと思います。
このお盆という節目に、今一度自身の使命を自覚し、私達が御先祖さまから何を受け、何を次世代に伝えるべきか、また何をもってご先祖様に報いていくことができるか、それを問い続ける機縁にしましょう。是非ご参拝されますよう心よりお待ち申し上げます。
国柱会霊廟賽主 田中壮谷