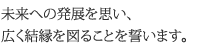宮澤賢治は岩手県花巻に生まれた。家業は古着質商であったが、浄土真宗の信仰あつい家庭で、3歳ごろ、すでに「正信偈」「白骨の御文章」を暗誦したと言われている。周知のように、賢治は盛岡中学を卒業した18歳の秋、島地大等編『漢和対照、妙法蓮華経』を読んで身ぶるいするほどの感動をしたというが、そこには幼時から育った家庭環境の影響があることは否めない。盛岡高等農林学校農学科第二部(現岩手大農芸化学科)に進学してからは、いよいよ『法華経』の信仰が深まった。賢治が国柱会に入会したのは大正9年で、同年12月2日付の友人保坂嘉内あての手紙に、「今度私は国柱会信行部に入会致しました」とある。しかし大正7年2月末から妹トシの病気看病のため母と共に上京し、翌8年2月まで滞京するが、その間に智学先生の講演を鶯谷の国柱会館で1度聴聞したことがあると前記の手紙にあるから、国柱会を知ったのはその頃であろう。
大正8年の編と推定される『攝折御文、僧俗御判』は、先生の『本化攝折論』および日蓮聖人御遺文からの抜き書きであるが、賢治の主体的信仰の確立はその頃とみられる。大正10年1月、父母の改宗を熱望していれられず、突如上京して国柱会館を訪れ、高知尾智耀講師から「法華文学ノ創作」をすすめられ、筆耕校正の仕事で自活しながら文芸による『法華経』の仏意を伝えるべく創作に熱中する。国柱会の街頭布教に従事したのもその頃だが、妹トシ病気のため帰郷する。賢治は『法華経』の信仰と科学の一如を求めたが、そのことは数多くの作品にも反映している。稗貫農学校(現花巻農業高校)の教諭時代、『植物医師』『飢餓陣営』の作品を生徒を監督して上演していたのは、国性芸術から影響されたものであることは確かである。農学校を退職して独居自炊生活に入り、「羅須地人協会」を設立して農村青年、篤農家に稲作法や農民芸術概論を講義したが、その発想も、やはり智学先生の「本時郷団」におうものといってよい。
賢治は昭和8年9月21日、『国訳妙法蓮華経』の頒布を遺言して永眠したが、法名「真金院三不日賢善男子」は国柱会からの授与である。大正11年11月に亡くなった妹トシの遺骨は三保最勝閣へ賢治が持参し、今は妙宗大霊廟に納鎮されている。賢治の遺形も、昭和57年の賢治五十回忌に大霊廟に納鎮され、申孝園には賢治の辞世の歌碑が建立された。賢治は、帰郷してから国柱会とは遠ざかったという説をなすものがいるが、最後まで国柱会の唱導する日蓮主義の信仰に生きたことは、森山一著『宮澤賢治の詩と宗教』や小倉豊文著『雨ニモマケズ手帳新考』などに明らかにされている。
故高知尾智耀講師「宮沢賢治の思い出」
一躍、国柱会信行員に入会
宮沢賢治という人は珍しい人で、生前は郷里の比較的少数の人々のほかは、ほとんど知られていなかった。その詩や童話などの作品も、少数の人々をのぞいては知られなかった。ところがその死後だんだんとその作品が世に知られ、その人格、信仰などが憬慕されるようになり、なかんずくその童話は若い人々に愛読されるばかりでなく、日本文学に希なるものとして高く評価されている。
それらの作品は、彼自ら呼んだように、法華文学といわれ、彼の持っていた純粋な法華経信仰からほとばしり出た珠玉の創作で、そのかおりは高く、純に、気品あり、滋々たる味わいがあって、長く愛好せらるるという性質のものである。
しかし、彼は詩人とか、創作家というばかりでなく、その専門的研究ともいわるべきものは、盛岡高等農林学校(註 現在の岩手大学農学部)の特待生として、また卒業後の研究による農業のりっぱな指導者として、農民指導の実績を示している。
ことにその人となりにいたっては、これは彼の天性というか、仏教信者たる父の影響というか、これまた世に珍しい慈悲のふかい、無欲恬淡な情厚い人であった。ことに求道的ともいうべく、中学生時代から仏教に接近し、仏教講話、経文などを好んで研究した。法華経は島地大等氏の教席にも出て、またその編著『妙法蓮華経』を愛読した。
彼が国柱会を知り、その創始者であり総裁であった田中智学先生を知ったのは彼が学生時代ならびに卒業後に、東京へ出て上野図書館にしばしば行った時、鶯谷にあった国柱会館に来た時からであろう。とにかく彼が妙法蓮華経々文を拝読して非常な霊感をうけ、それから進んで法華経の研究、そしてついに求道の熱情から信仰生活を欣求し、それをみたすために国柱会に入会することを決意し、彼の従弟で、親友であった関登久也氏を説きふせて、共に一躍国柱会の信行員の認可を申請してきたのである。
当時、国柱会中央事務所であった国柱会館で、国柱会統務会々長であった保坂智宙居士と、理事であった私とが、その願意を検討した結果、信行員の入会を承認し、御本尊妙法曼荼羅と、妙行正軌、宗章等を授与したのであった。いうまでもなく田中智学先生拝写の佐渡始顕の妙法曼荼羅であり、先生撰定の御修行の作法書、妙行正軌である。
のちに関登久也氏の語るところによれば、賢治は妙法曼荼羅を拝受して非常に喜び、花巻町の経師屋に命じて最もよき表装をなさしめ、そのできあがるや、妙行正軌にある御開眼の作法にもとづき賢治自ら式長として御開光の式をあげ、自分の拝受のものをすましてから、さらに関登久也氏感得のものも賢治が導師として御開眼したということである。その態度はじつに謹厳そのもので、音吐朗々として読経唱題の声いまなお忘れがたいと、関登久也氏は後に語っていた。
その後彼は、その妙法曼荼羅に対し奉り、日々妙行正軌によって御修行をなし、後年かの下根子桜の仮寓で自炊生活をして地方農家の子弟の指導にあたっていた時も、つねに二階にその御本尊を奉安し、妙行正軌による御修行をつづけていた。
賢治は国柱会信行員となるや、御修行を怠らなかったばかりでなく、正しい信仰の広布に全力をつくした。すなわち父上をはじめとし、家族や親戚の人々、またあらゆる人々に対して機会あるごとに国柱会の正しい信仰を鼓吹したのである。田中智学先生の統裁される日刊『天業民報』を拝読後は、門前に掲示板をつくって日々掲出し、田中先生著の各種の伝道用パンフレットを求めては、各方面に施本して精読をすすめた。また親戚および親しき人々と相会して御修行または信仰座談会をひらいた。そして彼自身は田中先生の著書はほとんどこれを読破し、なかんずく『日蓮主義教学大観』を精読し、同じく先生監修の『類纂高祖遺文録』などの拝読を怠らなかった。
国柱会館での奉仕
私がはじめて宮沢賢治に会ったのは、大正10年1月27日の午後、国柱会館の玄関先である。私は国柱会の講師であり理事である上に、会館の清規奉行として受付まで引き受けているという有様で、かなりいそがしい役目であった。
一人の青年の来訪に、玄関先へ出てゆくと、頭は五分刈、紺ガスリの和服姿に、洋傘と風呂敷づつみをもった、質実そうな二十五六歳の青年が立っていた。用向きをたずねると
「私は昨年、国柱会の信行員として入会をゆるされた岩手県花巻の宮沢賢治というものであります。爾来国柱会のご方針にしたがって信仰にはげみ、一家の帰正を念じて父の改宗をすすめておりますが、なかなか了解してくれません。これは私の修養が足らないために父の入信が得られない、この上は国柱会館へ行って修養をはげみ、その上で父の入信を得るほかはないと決意し、家には無断で上京して来たものであります。どういう仕事でもいたしますから、こちらに置いて頂きご教導をいただきたいのです」ということであった。
私は同君が昨年、関登久也氏と共に一躍信行員として入会されたことは思い出したが、家を無断でとび出してきたといわれるので、即決的にきめかねて
「東京にご親戚はありませんか」と尋ねると
「あります」
「それではひとまずそちらへおちついて下さい。そしてこの国柱会館に『毎夜講演』といって、日蓮主義の講演が毎夜あるから、それへ御来聴下さい。その際にゆっくりご相談いたしましょう」といって別れたのであった。
あとから考えると、玄関先の立ち話で帰したということは、いかにも不親切であったと思うが、その時の私は「無断家出」というのに、「それではマア居ってごらんなさい」とはいいかねて、お断りしたのであった。この時の状況は、関登久也氏へ送った手紙の中にややくわしく書かれており後に関登久也氏の著された『宮沢賢治素描』の中に出ている。
私が宮沢賢治にはじめて会った時の第一印象は、「誠実醇朴な青年」という感じで、この人が珍しい信仰家であり、たぐいまれな詩才を有し、親には至孝、農村指導の篤行家であったことは、まだ私にはわからなかった。
賢治が親戚といったのは、日本橋にあった商業上取引の家で、一晩はそこへ泊まったが、その後は本郷辺の筆耕屋へ住みこみ、持ち合わせの小遣いも少なく大変苦労されたということが後にわかったが、その時は何もそういうことはいわれなかった。もしそういう実情とわかったならば、及ばずながら何らかのお世話ができたのにと、何年か後に悔いたことである。
とにかく賢治はその後、毎夜国柱会館に通い、講話を聞かれるばかりでなく、いろいろの会合の斡旋をしてくれた。この国柱会館は、田中先生が大正5年に国柱会の中央活動の道場として建てられたたもので、本部は静岡県の三保の松原、最勝閣にあった。
国柱会館の建物は、洋風2階建てで、屋上は全部庭園になっており、2階は大広間で舞台があり、千人位の収容力があり、講演会、国性劇の公開等がたびたび行われた。『毎夜講演』は、国柱会の講師が交替で、法華経の話、日蓮聖人の御遺文の話、田中智学先生の『妙宗式目講義録』の話、その他日蓮主義による時事問題、社会問題の批判等を毎晩やっていた。
また当時は大正9年に日刊『天業民報』が創刊されてまもないころで、国柱会の講師と会館詰めの青年は、毎日のようにお昼休みを利用して、ほど近き上野公園に行き『天業民報』を施本し、読者を募るべく屋外宣伝をやった。賢治もおりおりこれに加わり、壇上に立って講演をされたそうである。私はいっしょになったことはなかったが、のちに他の青年から賢治が熱心に絶叫されたという話を聞いた。

国柱会館(昭和43年1月まで上野桜木町1番地に所在)
法華文学の創作
その間に私はしばしば賢治に会って信仰談を交わしたが、その時の私の話がもとになって、賢治が法華文学の創作に志したということは、帰寂の後になってはじめて私もこれを知った。
それは彼の原稿などの入っていたトランクのふたの裏のポケットから、一冊の手帖が出てきた。その手帖の中にこういうことばがある。
高知尾師ノ奨メニヨリ
法華文学ノ創作
名ヲアラハサズ
報ヲウケズ
貢高ノ心ヲ離レ
私には法華文学の創作をすすめたという明確な記憶はないが、いろいろ信仰上の意見を交換した中には、当然私が田中智学先生から平素教えられている、末法における法華経修行のあり方について、熱心に話したことと思う。すなわちいわゆる出家して僧侶となり仏道に専注するのが唯一の途ではない、農家は鋤鍬をもって、商人はソロバンをもって、文学者はペンをもって、各々その人に最も適した道において法華経を身によみ、世に弘むるというのが、末法における法華経の正しい修行のあり方である、詩歌文学の上に純粋の信仰がにじみ出るようでなければならぬ、ということを話したように思う。
それを聡敏な賢治は、私が法華文学の創作を勧奨したと受けとったのであろう。それが「高知尾師ノ奨メニヨリ 法華文学ノ創作」となったのではなかろうか。
ここで賢治のいわゆる『法華文学』について一言しておきたい。これはかつて雑誌『宗教公論』にも書いておいたが、創作そのものが、法華経を取り扱っているとか、仏教信仰を材料として取り扱っているとかいうのではない。童話であろうが、心象スケッチであろうが、短歌、俳句であろうが、法華経の正しい信仰をもった作者が、その信仰のやむにやまれぬ発露として表現された芸術的作品を、法華文学といったように思う。すなわちその作品の材料と共に、それらをとりあつかった作者の心的作用が非常に重んぜられている。であるから「名ヲアラハサズ 報ヲウケズ 貢高ノ心ヲ離レ」という条件がついてくるのである。
賢治が関登久也氏に送った手紙の中に、
「おお、妙法蓮華経のあるが如く総てをあらしめよ」とか
「これからの宗教は芸術です。これからの芸術は宗教です」とか、また
「いいものを書いて下さい。文壇という脚気みたいなものから超越して、しっかり如来を表現して下さい」などとかいているのを見ても、賢治のいわゆる妙法蓮華経の芸術的結晶、如来の文学的表現をさしているものと思われる。
上京の当時、賢治は神田の下宿に帰っては、非常なインスピレーションで筆をとり、この半年あまりの滞京中の創作力の旺盛なことはおどろくばかりで、ある月には原稿用紙三千枚にも上ったということであり、後年発表された童話や詩歌など、行李一ぱいあったという。
彼の文学は、それが詩歌であれ、童話であれ、短歌であれ、劇であれ、表面には法華経のホの字も出ていなくとも、また宗教や道徳とは直接関係のないようなものでも、その中には、天地宇宙の大真理たる法華経の大精神が、何らかの色となり香りとなって、芸術的に織り込まれているのである。その活きた力が、しらずしらずの間に人間の真実に感受して、霊的影響をおよぼさずにはおかないというのが、賢治の法華文学の真価値というものであろう。
また彼の手帖の中に
筆ヲトルヤマヅ道場観、奉請ヲ行ヒ所縁仏意ニ契フヲ念ジ、然ル後ニ全力是ニ従フベシ。断ジテ 教化ノ考タルベカラズ!タダ純真ニ法楽スベシ。タノム所オノレガ小才ニ非レ。タダ諸仏菩薩ノ冥助ニヨレ
とある。われわれは妙法曼荼羅御本尊に対し、国柱会所定の妙行正軌によって御修行をするその順序が、まず『道場観』で、次に『奉請』を唱えて本仏の来臨を念じ奉るのである。であるから、宮沢賢治にとっては、創作に従事するのは、妙法曼荼羅に対し奉り御修行するのと同じ心地に住して筆をとるというのである。
かくして出来上がるものが、彼の法華文学である。なんという気高い動機であろうか。なんという崇高な運筆であろうか。なんという法華純信の所産であろうか。
賢治の創作が不朽の生命を持ち、不滅の感化を及ぼすとすれば、それはじつに彼が忠実なる国柱会信行員としての、純信の賜であるというほかはない。
帰郷後のこと
賢治が上京の年の9月、妹トシ子さんが病気であると聞いて、東京を引きあげて帰郷した。その時国柱会館へきて、丁寧に挨拶して辞去された。それまでの間私はしばしば賢治と会ったが、彼はどちらかといえば無口な方であり、私も平素多忙でゆっくり話し合う機会は不十分であった。殊に私が非常に遺憾にたえないのは、この青年を田中智学先生に紹介する機会のなかったことである。賢治が国柱会館をうたった心象スケッチの中に
大居士は眼を病みて
三月人を見ず
とある通り、先生はあたかも眼病の治療中で、やむを得ない用のほかはあまり人に面会されなかったのが、その時の実情であった。
妹トシ子さんは非常な秀才で、目白の女子大学を卒業、郷里の女学校の教師をしていたようだが、賢治は大変この妹さんを愛していて
「私の家族中で一番私の信仰を理解し、同情をもっているのはこの妹です」
といって、力にしていたようだ。
大正11年の11月27日にトシ子さんが亡くなられ、賢治が非常に悲しんだことは、妹を弔う彼の詩篇によって明らかである。トシ子さんの死去に際しては、その法号を国柱会へ願い出て『教澤院妙潤日年善女人』と授与された。そして彼はその遺骨を抱いて、当時国柱会本部のあった静岡県三保の最勝閣に行って、お骨を納めた。その後本部が一之江に移ってその遺骨も妙宗大霊廟に移しまつられ、不断の回向供養を受けている。納骨はだれによってなされたか明らかでなかったが、先年私が宮沢家を訪問した際、母堂のいちさんに尋ねたところ、やはり賢治自身が奉持して最勝閣へ行かれたとのことであった。
賢治が郷里に帰った後は、時折文通があった程度でくわしい事情はわからなかった。大正13年の4月、彼がはじめて詩集『春と修羅』の第1集を出した時、私のところへも贈ってくれた。これに対して、私は礼状と共に私の感想をのべたと記憶する。
それは田舎風の質実な表装で、内容は彼のいわゆる心象スケッチが大部分であったが、簡単に言えば、私は難解な感じを与えられた。しかしどことなく天才的なひらめきが各所にあって、珍しい創作であるという感じはしたものの、少数の同好者のほかには、大衆的には愛好せられないのではなかろうかと思われた。それでそのことを賢治に手紙で書き送ったと記憶する。
賢治はその後、岩手県稗貫農学校(後の県立花巻農学校)の教諭となり、5年間特色ある教育をされた。退職後はかねての理想を実現するために、下根子桜というところにあった彼の家の小屋に独居自炊をはじめ、『農民芸術綱要』を執筆したり、『羅須地人協会』という農民道場のようなものを組織して、熱心に農民指導に従事し、ひたすら農村青年の幸福と向上につくされた。また肥料設計事務所を設け、無料で肥料相談に応じたりするうち、過労がもとで病気となり、生家の2階で療養するようになった。
そのころに書いたものであろうが、最後の手帖の中に
快楽もほしからず
名もほしからず
いまはただ
下賤の廃躯を
法華経の捧げ奉りて
一塵をも点じ
許されては
父母の下僕となりて
その億千の恩にも酬い得ん
病苦必死のねがい
この外になし
とある。彼の信仰的熱情がよく現れている。
最後に貰ったハガキ
私と賢治との間の文通はあまり多くはなかった。今私の手元に残っているのは、彼の臨終の年である昭和8年の年賀状だけで、その添えがきに
「客年中は色々と御心配を賜はり難有奉存候。お蔭様にて此の度も病漸くに快癒に近く、孰れは心身を整へて改めて御挨拶申上候」
とある。しかしその後なんら聞くところなく、その年の9月21日、37歳を一期としてついに不帰の客となられたことは、
何とも心残りの限りである。もし語りあう機会があったとすれば、賢治は、改めて何をいおうとしたのであろうか。
国柱会から授与された法号は、『真金院三不日賢善男子』という。
その臨終のことは、私は彼の死後に知ったのであるが、お父さんが、最後に何かいい残すことはないかといわれたところ、私の死後、国訳法華経を1000部印刷して私の知己朋友に贈って頂きたい、そしてその本の終わりに、左の言葉を印刷して貰いたいと口述したという。
合掌 私の全生涯の仕事は、此経をあなたの御手許に届けそして其中にある仏意に触れてあなたが無上道に入られん事を御願ひするの外ありません
昭和八年九月二十一日
臨終ノ日ニ於テ 宮沢賢治
彼がその死後にまで、かくのごとく周匝に遺言して法華経の正信を鼓吹されたということは、全く法華経のためにその一生を捧げたといっても過言ではない。
この『国訳妙法蓮華経』は、賢治の帰寂後遺族によってりっぱに印刷され、各方面へ賢治の遺志として寄贈されたが、私はその後、板垣征四郎大将の未亡人から、故大将のところへも送られ、大将は平素陣中においてこれを愛読せられ、その最後に先立ってはその信仰も進まれて、家人への手紙の中にも法華経信仰のことばがしばしば書き送られたということを承って、賢治の遺志は意外な方面に影響を与え、これからも与えるであろうと思われたことであった。
私は目下国柱会本部にあって、毎朝妙宗大霊廟に参拝、恩師師子王院智学日謙大居士の報恩謝徳を念じ、あわせて真金院三不日賢善男子の霊名が納鎮されている妙塔に対し、お題目を高唱して、菩提増進を祈っている。
病のゆゑにもくちんいのちなりみのりに棄てばうれしからまし
と辞世された賢治は、私の唱題を何と聞いているであろうか。
(高知尾智耀著『わが信仰わが安心』真世界社刊より)
高知尾智耀講師
同人号白瑞、本名誠吉。明治16年、千葉県に生れる。早稲田大学在学中、高山樗牛の文章に感銘、樗牛追悼会で、智学先生の講演をきく。千葉県成東中学、福島県磐城中学へ奉職。最勝閣(静岡三保)の講習会に参学。明治44年に入会。大正3年、教員を辞職して、最勝閣に本化大学準備学会教授として奉職、内護同人に列せられる。以来国柱会理事、天業青年団幹事長、明治会講師などを歴任。恩師滅後は統務または講師長老として本部方城に居住して会務に精励、60有余年の長い歳月法の為に献身し昭和51年8月5日、92歳をもって帰寂。